昨日、欧州委員会は、2026年にSNSの利用をさらに厳格に規制する新しい法案を提出する方針を固めました。この法案には、未成年者によるSNSの利用を禁止する規定が盛り込まれる見通しとのことです。このニュースを見て、そういえば、今ネパールで大変な事態が起きている。その発端はSNSを禁止する法案の実施だったはずだと思い出しました。
そこで思ったのですが、「SNSを禁止することで世の中がひっくり返るような事態が本当に起きるだろうか?」と。ネパールで起きたZ世代主導の抗議運動は、SNS規制をきっかけに爆発的に広がり、若者が街頭に繰り出し、国家施設まで攻撃する事態に発展しています。Z世代とSNSの結びつきが社会を動かすこと自体はどの国でも見られる現象ですが、国家の存続に関わるほどの危機にまで至るのは、どうにも腑に落ちないところがあります。多くの人々の思いが一つの方向に向かって爆発しなければ、これほどの事態には発展しないはずですが、その「核」となるものが見えにくい。ネパールのZ世代が一体何を目指していたのかが分かりにくいと感じ、自分の理解が足りないと自覚したので、少し調べてみることにしました。
歴史の革命と比べて
歴史を振り返れば、若者が主導した革命は数多くあります。フランス革命は「自由・平等・博愛」を掲げ、ロシア革命は「労働者の国家」を、そして中国革命は「民族独立と平等社会」を謳いました。こうした理想は現実の壁に砕かれ、多くの犠牲を生みましたが、それでも「理想郷を信じる力」があったからこそ、人々は過激な行動に走ることができたのです。
日本でも、我々の前の世代はまさに学生運動の時代でした。「世界を変えてやる、変えられる」と信じていたからこそ、時に内ゲバで仲間を殺し、無関係な市民を巻き込むような悲劇的行為すら「必要悪」として突き進んだ。それでも、その先に理想の実現があると信じていたからこそ続けられたのだ、と私は理解しています。
私自身の経験でいうと、「ピープルパワー革命」あるいは「EDSA(エドゥサ)革命」と呼ばれる1986年のフィリピン・マルコス政権の崩壊や、私が駐在中に目の当たりにした1998年のインドネシア・スハルト大統領の退陣などをリアルタイムで追ってきました。こうした“革命”と呼ばれる事件は、若者の不満の爆発と、理想を取り戻そうとする強烈なエネルギーが牽引していたのだと実感しています。
ネパールZ世代の運動の特異性
ネパールではSNSが単なる娯楽の道具ではなく、情報のやりとりや意見表明の主要な手段として広く使われてきました。都市部の若者だけでなく、地方に住む人々にとっても、FacebookやTikTokはニュースを知る窓口であり、日常の通信手段でもあったのです。
そうした状況の中で、政府は「偽情報の拡散や治安悪化につながる」との理由からSNSを一斉に停止しました。しかしそれは、若者にとって「声を奪われた」という強烈な体験となり、抗議行動が一気に燃え広がる引き金となりました。
もっとも、今回のネパールのZ世代の行動には、過去の革命のような「理想国家のビジョン」はあまり見えてきません。私も“にわか”なので正確さに欠けるかもしれませんが、彼らを動かしたのは次のような要素ではないかと思います。
- 汚職や縁故主義への怒り
- 雇用不安や格差への不満
- SNS禁止による「声を奪われた」感覚
これらはきわめて切実ですが、同時に「嫌なものは嫌だ」という感情の爆発にとどまっているように見えます。つまり、「潰したいもの」はあっても「築きたいもの」が見えてこないのです。
利用される若者のエネルギー
結果として、政権は倒れました。しかし暫定首相に座ったのは元最高裁長官。軍や官僚、国際社会が受け入れやすい人物です。つまり、若者の爆発が生み出したエネルギーの果実を手にしたのは、既存の体制にとって無害で都合のよい代理人のように見えます。
歴史は繰り返します。理想を掲げた革命ですら、その後の経緯の中で最終的には既得権益に吸収されてきました。私が経験したフィリピンやインドネシアのケースでも、そのような側面が少なからず見られました。勿論、改善された部分も多々ありますが、時の経過とともに既得権益層が復活を遂げるというパターンも繰り返されています。出発点が「理想の実現」であった革命ですら、長い年月を経て振り返れば、純粋な理念が狡猾な権力層に利用されてしまう例は多い。まして、今回のネパールのように「理想の実現」よりも「不満の爆発」が色濃く感じられる事態は、なおさら利用されやすいのではないか――そんな印象を受けます。
これはZ世代の革命か
過去の革命は「理想を掲げ、その実現を信じて突き進む」型が主流でした。私たちの前の世代――全共闘世代――はまさにそうで、理想のために過激化していく姿を私たちは子どもとして見聞きしてきました。さらに私自身は、1986年のフィリピン(TV越し)と1998年のインドネシア(駐在中に現地で)をリアルタイムで追い、その「理想を取り戻そうとするエネルギー」の熱量を肌で感じた記憶があります。
今回のネパールのZ世代の抗議は、その型とはだいぶ異なって見えます。彼らの前面にあるのは、「汚職や縁故への怒り」「雇用・格差への不安」「SNS遮断で声を奪われた感覚」といった、より直接的で切実な感情ではないか――そんな印象を受けます。デジタル環境に馴染んだ世代特有の「嫌なものはミュート/ブロックする」という行動様式が、社会運動のスタイルにも表れているのかもしれません。だからこそ「潰したいもの」は明確に見える一方で、「何を築くのか」という出口は少し見えにくい。私の理解は限られた材料に基づく個人的感想に過ぎませんが、今回のネパール騒動は、ここで挙げた革命と同じ類のものといえるのでしょうか。少なくとも社会の体制を変えたという点では、そう呼んでも良いように思います。仮にそうだとしても、革命のスタイルが静かに変わりつつあるのではないか――そんな印象を受けています。
結語
ネパールのZ世代が求めたのは、「理想の国家像」そのものよりも「今の不正義をもう我慢しない」という感情の表出だったのではないか――そう思っています。歴史を振り返れば、理想を掲げた運動ですら最終的に既得権に回収される局面は少なくありません。であれば、理念の輪郭が薄い今回の抗議は、なおさら利用されやすいのかもしれない、という懸念も拭えません。
ただ、1986年や1998年の出来事がそうであったように、時間が経って初めて見えてくることもあります。したがって、これを「Z世代の革命」と呼ぶのは早計かもしれませんが、今はそう感じています。ある程度時間をおいて、もし機会があれば、もう一度この出来事を振り返ってみたいと思います。


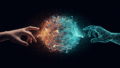
コメント