楽章間の拍手について考えた夜の、思いがけない後日談
先日書いたこの記事
楽章間の拍手について考えた夜 〜オランダと日本、クラシックコンサートの習慣の違い〜
実はこれには思いがけない後日談がありました。
あの時のオランダ・フィルハーモニー管弦楽団の結成40周年記念のオープニング・コンサートは、縁あって招待されたものでした。コンサートの後、ホワイエでワインを飲みながら談笑する場が設けられており、楽団の関係者のみならず、主な演奏者も参加していました。
とはいえ、常任指揮者やコンサートマスターのまわりにはたくさんの人だかりができており、しかも関係者の集まりなので、私のような部外者は少なく、そこに加わったとしても、クラシック音楽関係ではない私は、恐らく話にもついていけません。ましてや「記念に1枚写真を撮ってもらっていいですか?」などと言える雰囲気でもないので、「へぇ~、ヨーロッパってこんな感じなんだぁ。日本でもやってるのかなぁ」と思いながら眺めていました。
「楽章間の拍手」をめぐる会話
しばらくすると、オランダ・フィルハーモニー管弦楽団の古くからのスポンサーであるヤクルトの方や、私を招待してくださった楽団の職員の方、顔見知りの人たちも来られて、皆で歓談していました。
そこにまた楽団の方が寄ってきて、「今度新しくメンバーに加わるパクさんです」と紹介してくれました。そして今日のコンサートの演目などについて話が弾みました。
そんな中、私はふと、前の記事でも触れた“楽章の途中で拍手をするかどうか”という話題を口にしました。私から話したことの要旨は以下の通りです。
- 日本では私たちの世代は小学校の音楽の授業で「拍手は全曲が終わってから」と教わってきたので、それが常識だと思っていた。
- でも、こちらではほぼすべてのコンサートで楽章の間に拍手が起こるので驚いた。
- そこで。ニューヨークにいるクラシック通の先輩にも聞いたが、ニューヨークでも似たような状況だとのこと。
そして、最後に私は尋ねました。
「これって、正しいしきたりやマナーはどうすることなんですか?」
すると隣にいたパクさんが少し考えて、「確かに昔はそう言いましたが、今はその時々ですかね。場所とか聴衆によって変わりますね。」と、にこやかに答えてくれました。
「私もそう解釈していたんですが、今日のコンサートでは誰一人、楽章の間に拍手する人はいませんでしたよね。それで、私はますます分からなくなって…」
と言うと、楽団関係者の方がこう返されました。
「今日は、いつもうちの演奏を聴きに来てくれる昔ながらのファンの方が多いので、そういうことも暗黙の了解になっているんだと思います。」
するとパクさんが逆に私に尋ねました。
「クラシック音楽が生まれた頃はどうだったか知っていますか?」
これは以前、バッハ・コレギウム・ジャパンの首席指揮者に聞いたことがあったので、私はこう答えました。
「ええ、19世紀以前の演奏会では、観客は今よりもずっと自由に声を上げたり拍手をしたりしていたらしいですね。」
するとパクさんはにっこり微笑んで、
「そう、その通り。だから、その時々ですね。」
と返されました。
こうして楽しい時間を過ごしたのち、パクさんたちは別のテーブルへ移っていかれました。
後から知った「相手の肩書」
その時点では、ただの音楽好き同士の雑談という感じで、相手がどういう人なのかなど、特に気にも留めていませんでした。
年齢も職業も国籍も異なる人たちと、クラシックという一つの話題で会話を楽しみ、いい時間を過ごさせてもらいました。それだけで十分だと思っていたのです。
──ところが、家に帰って落ち着いたところで、その日に貰ったオランダ・フィルハーモニー管弦楽団の機関紙を眺めていました。
英語の文章を読むのは、仕事以外だと少し構えないと読む気にならないので、パラパラとページをめくっていると、見おぼえのある顔が目に入りました。
「あれ? 見たことがあるような……」
そこで改めてそのページを見てみると──なんとパクさんではありませんか。
Kyungmin Park、新任副指揮者に就任

Kyungmin Park(キョンミン・パク)。
来シーズンからオランダ・フィルハーモニー管弦楽団とオランダ国立オペラのassistant conductor(副指揮者)に就任。
……そう、私はよりによって専門家中の専門家相手に、拍手のマナーについて“語り合っていた”のです。
気づいた瞬間、思わず声が出ました。
「おいおい、何を偉そうに語ってたんだ俺は」と。
けれど、笑いながらもどこかで少し焦りを感じました。
肩書きが変える、会話の空気
私はその人が副指揮者だと知った瞬間、真っ先に「何か失礼なことや的外れなことは言わなかっただろうか?」と思いました。
それまでまったく気にせず、肩書を知らないまま対等に話していたはずの空気が、頭の中で少し変わるのを感じたのです。
まるで、同じ会話を別の色のフィルターで見直すような感覚でした。
この感覚を自覚した時、あのとき感じていた安心感や自由さは、「知らない相手だったからこそ」生まれていたのだと改めて思いました。
相手を“肩書き”で見ないということは、実は人と話すうえでの、いちばんの贅沢なのかもしれません。
肩書のない対話という贅沢
思えば、私たちは日常のあらゆる場面で、知らず知らずのうちに相手の名刺や立場を先に見ています。会話が始まる前に、どこかで“位置づけ”を決めているのです。
そしてそれが外れると、途端に人間らしいやり取りが生まれます。
社会的な肩書きというものは、便利で、同時に不自由でもあります。
それがあることで会話がスムーズに進むこともあれば、
それによって言葉が窮屈になることもあります。
この夜の出来事は、そんな当たり前のことを、ちょっと恥ずかしい形で思い出させてくれました。
「肩書のない対話」というのは、もしかしたら今の時代、最も贅沢な時間なのかもしれません。
相手を“知らないまま”話す。
その無防備さの中に、人間らしい自由があるのだと思います。
あの日の演目であったブラームスの交響曲第1番、通称”ブラ1”を聞きながら、あの夜のロビーのざわめきと笑い声を、今も思い出しています。

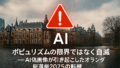
コメント