クラシック好きに必ず聞かれる質問
クラシック音楽の話題になると、よく聞かれる質問があります。
「どんな曲が好きなんですか?」
「誰が好きなんですか?」
クラシックにあまり馴染みのない人ほど、こうした質問をすると「自分の知らない名曲や、もっとマニアックな作曲家の名前が返ってくる」と期待しているようです。ところが実際に返ってくるのは意外なほど“普通の答え”。そのギャップに、少し驚かれることが多いのです。
私の正直な答え
私はクラシックの専門家でも評論家でもありません。ただ、子どもの頃から聴き続けてきた一人のリスナーとして、正直に好きな曲を答えると──
- 交響曲なら 第九(ベートーヴェン交響曲第9番) や ベト7(交響曲第7番)、そして マラ5(マーラー交響曲第5番)
- 協奏曲なら チャイコン(チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲)
- 作曲家でいえば、やはり ベートーヴェン
どれも「クラシックに詳しくなくても名前くらいは聞いたことがある」ような有名曲ばかりです。
すると、多くの人は少し拍子抜けした表情をします。
「もっと奇抜な答えが返ってくると思っていたのに……」と。
王道の魅力は“誰にでも分かる”から王道
しかし、こうした「誰でも知っている曲」が選ばれるのには理由があります。
良いものは、素人が聴いても、通が聴いても、やはり「良い」のです。
第九の思い出
年末の風物詩として有名な第九ですが、私にとっては「元旦に聴く曲」でした。
父方の祖父の家に親族が集まり、大晦日深夜からおせち料理の準備をしている間、男性陣が火鉢を囲みながら語り合う。そのBGMが第九。夜明け前の静けさに流れる第4楽章の合唱は、新年の幕開けを感じさせるものでした。
ベト7との出会い
のだめカンタービレで有名になるずっと前から聴いていた曲です。初めて「これは良い」と思ったのは、赴任先ジャカルタで見たN響アワー。冒頭の力強いリズムと終楽章の推進力に圧倒されました。
マラ5の発見
映画『ベニスに死す』でも知られる第4楽章アダージェット。私がマーラーを知ったのはサントリーのCMでした。「やがて私の時代が来る」という言葉の通り、マーラーの音楽は当時の私にとって新鮮な発見でした。カラヤンのアダージェットを聴いたとき「世界一美しい旋律」と呼ばれる理由に納得しました。
チャイコンの思い出
大学受験期、友人に借りたテープが出会いでした。BGMのつもりが、何度も繰り返し聴くほど夢中になった曲。技巧的で華やか、でもどこか切ない旋律。アムステルダムに駐在して初めて生演奏を体験したとき、その感動はさらに大きなものとなりました。

アムステルダム・コンセルトヘボウにて。演奏後スタンディングオベーションに応えるソリスト
→ 詳しくは note記事「マイ・クラシック(1) ~ オランダ・フィルハーモニー管弦楽団」 に書いています。
こうした曲が「有名」なのは偶然ではありません。
王道と呼ばれるのは、それだけ普遍的な魅力があるから。
“通”の答えも意外と同じ
面白いのは、クラシック通に聞いても結局は同じ答えが返ってくることです。
もちろんディープな名曲も紹介してくれるでしょうが、「一番好きな曲は?」と問われれば、やはり第九やベト7といった王道が挙がる。
むしろ「通こそ、王道の偉大さを分かっている」と言えるかもしれません。
マニアックな作品を知っているからこそ、王道の価値が際立つ。
通が聴いても素人が聴いても、やっぱり良いものは良い。だからこそ有名になり、今も演奏され続けているのだと思います。
だから、こういう誰もが知っている曲を自分のベストだと答えたところで恥じることは全くないのです。
初心者は遠慮なく“王道”から
クラシック初心者ほど「知らない名曲を選ばなければならない」と思い込みがちです。
でも実際は、有名曲から楽しむのが一番の近道。
名曲と呼ばれる作品は、それだけで十分に魅力的で、聴く人を裏切りません。むしろ「みんな同じ曲を好きになる」ことこそが、クラシックの普遍的な面白さだと思います。
だから、もしクラシックに興味を持ったら、まずはベートーヴェンやチャイコフスキー、マーラーといった王道から。
そして「通も同じ曲を聴いて感動している」と知れば、安心して世界に入っていけるはずです。
まとめ
クラシック音楽は決して難しい世界ではありません。音楽を聴くのに特別な知識も必要ありません。
通も素人も、結局は同じ曲を選ぶ。なぜなら、良いものは誰が聴いても良いから。
マニアックな知識がなくても大丈夫。
むしろ「誰でも知っている曲」を堂々と楽しむことこそ、クラシックの一番自然な楽しみ方です。
そして、その体験を重ねるうちに、自分だけのお気に入りや思い入れのある曲が増えていく──。
それがクラシックと長く付き合う醍醐味なのだと、私は思います。

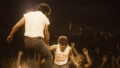

コメント