欧州のスーパーで寿司やラーメン、さらには「餅アイス」まで見かけることは珍しくありません。
まさに“和食ブーム”。しかし、その棚に日本企業の名前を探すと──驚くほど見当たりません。
なぜ、日本企業はこのブームに乗れていないのか。
商社で食品輸出に携わってきた私の経験から、その構造を解剖したのが noteマガジン「餅アイスで読み解く──欧州市場で勝つ日本食ブランド戦略」 です。
欧州市場における日本食品ブランドの現状と分析
本マガジンでは、日本食品の欧州市場での立ち位置を3本の記事で思想的ブランド構築という観点で分析しました。
- 和食ブームの担い手は日本企業ではなかった
- 【商社マンが構造解剖】「語る力」こそが勝敗を分ける──MOCHI ICE CREAMが示す、日本企業が学ぶべきブランディングの本質
- 【商社マンが構造解剖】品質“だけ”では勝てない──日本企業が主語を取り戻す思想型ブランディング
(そして第3話では「日本企業が主語を取り戻すための実践的アプローチ」を提示しています)
和食ブームの裏側から学べる3つの視点
note記事の内容については前回の本ブログの記事、欧州餅アイス市場の成長要因──日本企業が取るべき戦略 – ビジネス×構造×共感──商社マンの視点から で、要約していますので、興味のある方はぜひ一度読んでみて下さい。ここで浮かび上がったのは、日本企業が欧州市場で埋没してしまう「構造的な理由」でした。
私がこの記事を通して、提起しているのは次の3つの視点です。
なぜ日本食品は欧州の和食ブームで主役になれないのか
我々が普段食べている日本の加工食品会社の製品は、和食ブームと言われる欧州で認知されているのでしょうか?残念ながら殆ど目にすることはありません。
何故でしょうか?
味が合わない?そんなことないはずです。インバウンドで来た海外の人からも日本の洋食は支持されているというニュースを何度も目にしていますから。
「なぜ日本企業はこのブームに乗れていないのか?」この問いに対して、商社で食品輸出に関わってきた経験を元にその構造を徹底的に解剖してみました。
本記事では、流行の裏側にある「主役が日本企業ではない理由」を解き明かし、日本企業が市場を動かすプレーヤーになるためのヒントを提示しています。
食品だけに限らず、過去の歴史を振り返り欧州市場を席巻した自動車やエレクトロニクス製品とも比較もしていますので、食品ビジネスに従事していない人でも十分に楽しめる内容になっています。
食品ビジネスに携わるプロの方には、更に以下のことも得て頂けると思います。
- 「日本食ブーム」の表面的な見方に騙されず、市場の主導権を握る構造がわかります。
- 輸出戦略を立てる前に、陥りがちな「思考停止」から抜け出すためのヒントが得られます。
- 欧州でMOCHIが棚を取れた勝因である、日本的な「素材」と欧州的な「意味設計」の掛け合わせについて学べます。
そして、この問いを起点に、次の3つを考えていただきたいです。
- 自社の製品が“主語”になっているか、それとも他者の戦略に乗っているだけか?
- 欧州市場特有の文脈(ヘルシー、サステナブルなど)に翻訳できているか?
- 語り部=ブランドストーリーテラーを、他者に任せていないか?
ですので、食品ビジネスに従事している方もそうでない方も、ぜひ一度、noteのマガジンも覗いてみてください。(第1話は無料ですべて読めます)
日本食品ブランドが欧州で勝つための条件
「品質が良ければ売れる」という考えは、もはや欧州市場では通用しません。
MOCHI ICE CREAMの成功が示すように、勝敗を分けるのは “語る力”。
その具体像と実践策を、noteマガジンで詳しく解説しています。
👉 マガジンを読む


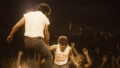
コメント